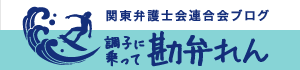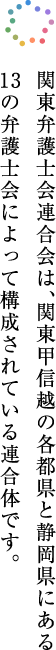
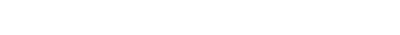 宣言・決議・意見書・声明等
宣言・決議・意見書・声明等
平成19年度 宣言
市民に開かれた家庭裁判所をめざして
家庭裁判所は、1949年、家事審判所と少年審判所を統合して創設された。家庭裁判所は、家裁調査官制度、家事調停制度などによって専門性と市民性を備え、また、司法でありながら福祉・教育的機能を併せ持っている。
家庭裁判所は、個人の尊厳と両性の平等を原則とする家族法の基本理念を戦後の日本に定着させ、また、少年司法を通じて少年の健全な育成に大きな役割を果たしてきた。
戦後60年が経過し、家族の在り方も大きく変わり、家族法と現実の家族関係との間に幾つかの矛盾が現れており、そのことが新しい家族関係の形成を困難にしている事例さえみられる。年間30万件余に至った離婚のうち、家庭裁判所に持ち込まれる割合は、僅か10%程度にとどまっており、その裏には、離婚しても養育費さえ支払われない様な深刻な現実が広がっている。内縁関係の増加、夫婦の別姓など多様化する家族の法的保護の問題、DV法、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法など、家庭内の人権問題など新しくて重要な課題が生れてきた。また、現代社会を反映した少年非行の発生の中、少年司法の在り方にも市民の目が向けられている。
関東弁護士会連合会は、家族法の基本理念が市民の隅々まで定着するとともに、多様化する家族の在り方を見据えた家族法とその運用を求め、また、少年の健全な育成を目的とする少年司法の理念が広く市民に理解され健やかな子どもたちの成長がはかられることを願って次のとおり宣言する。
第1 家事関係など
- 多様化する家族関係と家庭内の人権保護に配慮し、増加する離婚の中で、子どもなど弱者が充分保護されていない現実を考慮し、以下の法改正を求める。
- (1) 法制審議会が1996年に策定した別掲の「民法の一部を改正する法律案要綱」を実現すること。
- (2) 離婚における家庭裁判所利用率を向上させ、離婚給付・養育費等の取決めを広めるため、家庭裁判所に即決調停・即決和解的な離婚手続を導入すること。
- (1) 法制審議会が1996年に策定した別掲の「民法の一部を改正する法律案要綱」を実現すること。
- 近年、外国人の家庭裁判所の利用が高まっており、家庭裁判所手続において外国人の権利が正当に護られるよう、次の施策を求める。
- (1) 専門調停委員の拡充と通訳の確保
- (2) 外国の文化・慣習等の違いについてのマニュアルの整備や、裁判所庁舎設備やパンフレット等における多言語化の実現
- (3) 外国籍調停委員の採用の実現
- (1) 専門調停委員の拡充と通訳の確保
- 会内研修や各弁護士の職務遂行を通じてジェンダー・バイアスの解消に取り組むとともに、家庭裁判所に対し、その手続におけるジェンダー・バイアスを除去するため、調停委員の教育研修などの継続的実施を求める。
- 広く市民が家族法の保護を受けられるよう、会内に家事問題委員会を設置するなどして家事に関する啓発活動や家事相談を積極的に展開し、家庭裁判所係属案件の弁護士代理活動を飛躍的に伸ばすと共に、将来的には家事問題ADR等の活動を強化する。
- 家庭裁判所委員会につき、以下の配慮がされることを求める。
- (1) 委員が交代しても、規則に基づく運営がなされるよう、すべての家庭裁判所委員会で運営細則等を策定し、書面で備置し、委員委嘱時に交付すること。
- (2) これまでの家庭裁判所の関係者の範囲を超えて広く市民の声を反映させるため、行政で採用されている公募委員制度を導入すること。
- (3) 家庭裁判所委員会の議事と議事録を市民に公開するよう努めること。
- (1) 委員が交代しても、規則に基づく運営がなされるよう、すべての家庭裁判所委員会で運営細則等を策定し、書面で備置し、委員委嘱時に交付すること。
- 家庭裁判所は急速に利用が増加しており、市民の潜在的需要は、非常に大きく、市民生活にとって不可欠な存在であることにかんがみ、家庭裁判所がもっと市民に利用し易くなるために、手続の簡易化・合理化を図るとともに、人的・物的面での飛躍的整備・拡充が必要であり、その早期の実現を求める。
第2 少年関係
- 弁護士は、少年の健全育成を目的とする少年法の下においても、被害者やその家族(以下「被害者等」という)の権利や心情にも配慮した付添人活動を実践する。
弁護士及び弁護士会は、被害者等からの意見聴取等の現行少年法に定められた被害者等へ配慮した保護の諸制度が今後も維持され、かつ、これが適正に運用されるよう、家庭裁判所に対して、市民への制度周知を促すとともに、被害者等に対応する家庭裁判所調査官、書記官の増員などの施策を講ずるよう求める。 - 弁護士及び弁護士会は、少年司法の持つ福祉的機能こそが少年の成長発達に資することを十分理解し、これが維持拡大されるよう努める。
そのため弁護士は、少年の保護者、教師、雇い主、補導委託先、家庭裁判所調査官、鑑別所技官、児童相談所職員などの関係者と協力連携し、少年司法の福祉的機能が十分に発揮されるよう付添人活動を行う。
また、弁護士及び弁護士会は、家庭裁判所に対しても、少年司法における福祉的機能の回復、拡大を強く求め、これに反して安易な検察官送致や低年齢者の少年院送致が行われないよう求める。 - 少年に認められた付添人選任権を実質的に保障するため、当番付添人制度の全国的実施の実現に努めるとともに、国選付添人制度の対象範囲をさらに拡充する法改正が早急にされるよう求める。
2007年(平成19年) 9月21日
関東弁護士会連合会
法制審議会1996年策定「民法の一部を改正する法律案要綱」の概要
- (1) 婚姻適齢を男女とも18歳とする。
- (2) 再婚禁止期間を現在の6か月から100日に短縮する。
- (3) 選択的別姓の導入
- (4) 夫婦間の契約取消権規定の削除
- (5) 面接交渉につき「面会及び交流」として明文を置く。
- (6) 監護費用の分担義務について規定を置く。
- (7) 財産分与の考慮すべき要素を具体に例示し、寄与度が異なることが明らかでない場合は、いわゆる「2分の1ルール」を採用する。
- (8) 裁判離婚原因を見直す(5年間の別居を離婚原因に加える。過酷条項を加える。精神病離婚の規定を削除する。)
- (9) 失踪宣告の効果(取り消されて前婚解消の効力は失われないことを規定する。)
- (10) 嫡出子と非嫡出子の法定相続分を平等にする。
提案理由
- 市民に開かれた家庭裁判所をめざして
私たちは「市民に開かれた家庭裁判所をめざして」というテーマで、シンポジウムの準備を重ね、このテーマに次のような意味づけをしてきた。
第1に、市民にとって身近で利用し易い家庭裁判所
第2に、市民の声が届き、その声が運営に反映される家庭裁判所
第3に、「個人の尊厳と両性の平等」「少年の健全な育成」という本来の目的が、複雑化した現代社会の中で発展的に貫かれる家庭裁判所 - 戦前の家族制度は「家制度」と「男性上位」の上に成り立っていた。日本国憲法第24条は、個人の尊厳と両性の本質的平等を規定し、これを受け家族法制が根本的に改正された。
戦後地方裁判所の支部として設置された家事審判所と旧少年法下の行政機関であった少年審判所は、1949年(昭和24年)1月1日に統合され、家庭裁判所として新たに創設された。
以来、家庭裁判所は「個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持」(家事審判法第1条)と「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」こと(少年法第1条)等を目的とし、家庭をめぐる法律的な問題を総合的に扱う機関として出発した。
家庭裁判所は、司法でありながらも福祉・教育的な役割も担っており、また市民の家庭生活に直接関わる機関である。家裁調査官制度や医師の配置、膨大な数の家裁調停委員によって支えられてきた調停制度、そして参与員制度などは、これら家庭裁判所の目的実現に大きな役割を果たしてきた。 - 戦後の家族法制の根本的な改正、その後の都市化、核家族化の流れの中、家族の在り方は大きく変化してきた。
この間、個人の尊厳と両性の本質的平等の理念は、市民の家族生活に着実に定着してきたし、これを司法の面から支えてきた家庭裁判所の役割もまた大きいものがあった。
このようにして、家族法及び家庭裁判所は、戦後の日本の家族のありように全体として積極的な役割を果たしてきた。しかしながら、現実の家族のあり方は、家族法改正時の予想を超えて大きく変わりつつあり、成文法と現実の家族の在り方との矛盾が徐々に拡大している。 - 成文法・司法と現実の家族の在り方との矛盾は以下のとおり指摘することが出来る。
- (1)家族法は、個人の尊厳と両性の平等を定めながら、その多くを任意規定として家族の自治に委ねている。離婚件数は、この60年間に4倍にも増え、年間30万件近くになるが、離婚に対する司法の関与は僅か10%足らずである。養育費など子どもをめぐる取り決めは、大半が野放しの状態であり、家裁の保護の枠外にある。離婚の自由が認められているとはいえ、子どもの養育監護に悪影響が出ている現実は無視すべきでない。
- (2)家族法は、1896年(明治19年)に制定され、これに改正を加えたものである。そのため子に対する親の支配権を意味する親権や、嫡出子と非嫡出子に差をもうけるなどの規定が残されている。これらの規定は、憲法や子どもの人格と人権の尊重を規定した子どもの権利条約に違反するだけでなく、新しい子ども観・子育て観の定着の障害となっている旨指摘されている。
- (3)家族の多様化
戦後60年の間に、社会と家族は大きく変化し、次に指摘するように、現家族法が予定していない家族関係が現れてきた。家族関係の多様化は、経済・文化・生活の発展・変化の中で必然的にもたらされるものであり、家族法の規定自体が、新しい家族の在り方の障害となっている可能性があることを指摘せざるを得ない。
- ① 重婚的内縁のほか、単に婚姻届を提出していないという意味での内縁の増加
- ② 別姓を維持する夫婦の増加
- ③ 離婚についての破綻主義の考え方
- ④ 再婚禁止期間規定の不合理性と戸籍無き子どもの増加
- ⑤ 血縁関係や懐胎を前提としない親子関係の出現
- ① 重婚的内縁のほか、単に婚姻届を提出していないという意味での内縁の増加
- (4)夫婦・親子・家族間での人権
人権は、主として国家やこれに準ずる巨大な力と個人との関係で論じられてきた。 他方、家族は、愛情で結ばれた最小の自治組織として扱われ、仮に家庭内で暴行等があっても直ちには人権の侵害とは捉えられず、「しつけ」「夫婦喧嘩」などと見過ごされてきた。
しかし、このような家庭内の人間関係についても、人権の観点から把握すべしという考え方が主流となってきた。
家庭内の人権に目を向けたDV法、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法等は、日本の家族関係の在り方に大きな影響を与えようとしている。これらの法律は、家族法が想定していなかった内容を有しており、家族法の内容とその適用に新しい視点を与えるものである。
- (1)家族法は、個人の尊厳と両性の平等を定めながら、その多くを任意規定として家族の自治に委ねている。離婚件数は、この60年間に4倍にも増え、年間30万件近くになるが、離婚に対する司法の関与は僅か10%足らずである。養育費など子どもをめぐる取り決めは、大半が野放しの状態であり、家裁の保護の枠外にある。離婚の自由が認められているとはいえ、子どもの養育監護に悪影響が出ている現実は無視すべきでない。
- 民法の一部を改正する法律案要綱に基づく立法化について
- (1)1996年2月、法制審議会は「民法の一部を改正する法律案要綱」を決定し法務大臣に答申した。
この答申は、10項目にわたる民法改正を内容としており、改正の理由として、①婚姻及び離婚についての市民の価値観・人生観の変化多様化、 ②女性の地位向上のための世界的な努力、③選択的夫婦別氏制の導入を求める意見が強くなった、④有責配偶者からの離婚請求を認める判決の定着、欧米諸国では破綻主義化を明確にした離婚法が相次いでいること、⑤非嫡出子の相続分問題については、国際人権委員会から、国際人権規約に抵触する旨の指摘を受けていること、東京高裁での民法第900条第4号但書についての違法判決(但し、その後最高裁は合憲判決)の存在などが指摘されている。 - (2)この法律案要綱は、成文法と現実の家族関係との矛盾の多くを解消ないし緩和するものであり、それまで裁判所の解釈によって対応してきた点を、法律改正によって解決しようとするものであった。
日弁連は、要綱案の積極的側面を評価し、速やかに立法化されるべきとの見解を表明した。
しかしながら、選択的夫婦別氏制度の導入、非嫡出子の相続分同等化につき、様々な意見があるとして国会への提出が見送られた経緯がある。このような消極的な対応は、今般の再婚禁止期間の短縮法案の反対理由ともつながるものであり、成文法と現実の矛盾を一層大きくするだけであって、何ら問題を解決するものでない。
要綱案並びにその後の情勢の発展を踏まえた民法改正が速やかになされるべきである。
- (1)1996年2月、法制審議会は「民法の一部を改正する法律案要綱」を決定し法務大臣に答申した。
- 即決調停・即決和解制度について
- (1)離婚件数は年間30万件にも膨れ上がり、家庭裁判所での離婚事件の係属数も増加しているが、離婚全体の中での調停離婚・裁判離婚の割合は10%程度に過ぎない。利用率の低さの原因は必ずしも明確ではないが、離婚当事者にとって、家庭裁判所に何度も赴き、家事調停、人事訴訟を遂行することが、時間的にも精神的にも負担になっていることが一因ではないかと考えられる。
- (2)アメリカ・イギリス・フランスなど欧米では、当事者だけの協議離婚は、原則として認められず、仮に当事者間で離婚合意があっても、何らかの形で裁判所が関与し、離婚意思や養育費などの内容を確認している。韓国でも裁判所において離婚意思の確認がなされている。
当事者の離婚届のみで離婚が認められる制度は、国際的にみると特異といえる。離婚の自由の観点から、日本の協議離婚制度を評価する意見もあるが、「真意に基づかない離婚届が提出される」「養育費や財産分与の取決めがなされず子どもが放置されている」などの深刻な現実も指摘されている。また、年金分割制度がもうけられたが、裁判外での離婚合意では、この制度が充分利用されないのではとの指摘もある。 - (3)すべての離婚について裁判所が関与する制度の導入は、一つの方法であるが、現在の協議離婚制度を残したまま、離婚にあたり裁判所の利用を容易にし、かつ養育費、財産分与の給付をより確実にする方法としては、家庭裁判所における即決調停・即決和解的な離婚手続が考えられる。
これは、当事者間で離婚・親権者・離婚給付・養育費等につき、事実上合意がなされている事案について、双方出頭の上裁判所において離婚調停・離婚和解をするものである。
なお、離婚給付・養育費の取決めを要件にせず、離婚・親権者のみ合意している場合にも制度の利用を可能とすることもできるが、純然たる協議離婚制度を残存させる以上、それでは実益に乏しいと思われる。 - (4)即決調停は、現行法の枠内でも実施が可能であると思料される。
即決調停では、予め特定日(即決調停日)に当番調停委員が待機し、即決調停にあたることになる。
人事訴訟に即決和解を導入することについては、立法の手当が必要になると思料される。調停前置主義との整合性も課題である。
即決調停・即決和解ともに、弁護士等の専門家による協議を前提としている場合や、ADRと組み合わせることなどによって、より有効な制度となると考えられる。
- (1)離婚件数は年間30万件にも膨れ上がり、家庭裁判所での離婚事件の係属数も増加しているが、離婚全体の中での調停離婚・裁判離婚の割合は10%程度に過ぎない。利用率の低さの原因は必ずしも明確ではないが、離婚当事者にとって、家庭裁判所に何度も赴き、家事調停、人事訴訟を遂行することが、時間的にも精神的にも負担になっていることが一因ではないかと考えられる。
- 近年、わが国における外国人登録者数の増加とともに、外国人が家庭裁判所を利用する機会やそのニーズも確実に増大している。
しかしながら、弁護士と調停委員に対するアンケートの結果、外国人が家庭裁判所を利用するにあたり、通訳の手配ができず十分な意思疎通ができない、文化、宗教、慣習上の違いを調停委員が理解してくれない、家庭裁判所に対するアクセス方法がわからない、調停手続などの意味やその効果がわからないなどの不満や問題点が多く存在することが明らかとなった。
日本国憲法は、公正な裁判手続を利用できる権利を外国人にも日本人と等しく保障していることからすると、家庭裁判所は、外国人が家庭裁判所を利用するにあたっての上記障壁を取り除き、外国人にとって利用しやすい家庭裁判所とするため、計画的かつ継続的に取り組んでいくことが必要である。 - これまで弁護士会が調停委員として推薦した韓国籍の弁護士につき、家庭裁判所は就任を拒否してきた(2003年神戸家庭裁判所、2006年仙台家庭裁判所)。調停委員のみならず、司法に関わる職種については弁護士を除き、事実上外国籍を除外しているのが実情である。これは、1953年の内閣法制局がいう「当然の法理」(公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするとの見解)によっているとされる。
調停委員は、「専門的知識経験を有する者」「人格的識見の高い」者が任命され、その役割は当事者間の合意形成であり、仮に「当然の法理」を前提としても、調停委員の職務を公権力の行使であると解するのは無理がある。なお、破産管財人への外国人の就任は認められており、そのことと比較しても調停委員への就任拒否は不合理である。司法修習生として修習し、弁護士登録をして、長年にわたり司法に関わってきた人材につき、日本国籍を取得していないという理由のみで調停委員への任用を拒否することは、実質的に見ても著しく不合理な対応である。 - 国際社会においては、男女差別を解消し女性の地位向上のための様々な取り組みがなされ、わが国においても1999年に男女共同参画社会基本法が制定、施行されてから、憲法の保障する両性の平等を実質的に実現するため、社会のあらゆる場面における男女差別の解消及び男女共同参画社会の実現に向けた取り組みが行われている。
しかしながら、ジェンダー・バイアスは、無意識的に社会の伝統や慣習として自然に形成されてきたものであるため、個人によりその認識レベルの差は非常に大きく、ジェンダー問題に対する誤解や偏見も多く生じているのが現状である。このことは、調停委員に対するアンケート結果からも顕著であり、本来、人権救済の最後の砦たるべき司法手続において、ジェンダー・バイアスによる被害が生じているという現状は看過できる問題ではない。
弁護士会としての男女共同参画社会実現に向けた取り組みも決して十分なものとはいえない。弁護士会は、継続して会内部及び司法手続におけるジェンダー・バイアスの除去に向けた取り組みを行うべきであり、弁護士一人一人が、自らの意識や職務遂行過程に潜むジェンダー・バイアスの危険性を認識し、司法に携わる者としての責任を自覚して行動していくことが重要である。
家庭裁判所に対しては、調停委員の選任過程及び継続的な教育研修の場において、司法手続におけるジェンダー・バイアスの除去に向けた取り組みを行うことを求めるものである。 - 近年家裁で扱われる家事事件数は大幅に増加している(家事審判1989年25万件、2004年53万件、家事調停1989年8万5000件、2004年13万3000件、人事訴訟1989年6500件、2004年1万1000件、成年後見2004年2万件)。しかしながら、調停離婚、裁判離婚は全体の10%に過ぎない。家庭裁判所に対する潜在的需要は、はるかに多いが、家庭裁判所が市民にとってまだまだ遠い存在であり、家庭裁判所に出頭して解決すること自体にいまだ抵抗感がある。また、市民にとって家事調停、人事訴訟が面倒で複雑な手続なのである。
このような状況を踏まえ、家庭裁判所に対する市民の信頼を高め、利用を増加させるためには、少なくとも以下の対応が必要である。
- (1)学校教育や市民レベルでの法教育の普及と家族法・家庭裁判所についての理解を深める啓発活動を押し進めるべきである。また、市民が受動的に関与するだけでなく、裁判傍聴や裁判所見学等、主体的な取り組みを重視すべきである。
- (2)家庭裁判所に対する潜在的需要は極めて多いと思われるにもかかわらず、この需要に充分に応えられていないのが実情である。裁判官の調停関与、調査官の調査、書記官実務等々、家庭裁判所の本来の目的にそった活動をするためには、もっとゆとりを持って個々の事件にあたる必要がある。また、建物等の施設についても、必ずしも十分ではなく、当事者のプライバシーさえ守られていないことも散見される。家庭裁判所が市民の需要に応えるためには、人的・物的面での飛躍的拡充が急務である。
- (3)家事問題についての市民の潜在的法的ニーズは相当に大きいと思料される。しかしながら、家事問題について弁護士会として取り組んでいる単位会は少数であり、また、家事問題に積極的に関わる弁護士数もまだまだ少ない。広く市民が家族法の保護を受け、市民の潜在的法的ニーズに応えられるよう、弁護士会は、家事問題委員会を設置するなどして、家事事件についての弁護士と弁護士会の取り組みを強化すべきである。また、弁護士会は、家庭裁判所と連携して、家事問題についての啓発活動や家事相談を積極的に展開し、家事事件の代理活動を飛躍的に伸ばすとともに、将来的には、家事問題ADR等の活動を強化することが必要である。
- (1)学校教育や市民レベルでの法教育の普及と家族法・家庭裁判所についての理解を深める啓発活動を押し進めるべきである。また、市民が受動的に関与するだけでなく、裁判傍聴や裁判所見学等、主体的な取り組みを重視すべきである。
- 家庭裁判所委員会は、家庭裁判所内に設置された委員会ではあるが、広く市民の声を反映させるという司法改革の理念に基づいた組織である。家庭裁判所委員会が所期の目的に向かって発展するためには、家庭裁判所はもとより関係者の粘り強い努力が必要である。また、広く市民と手を携えて交流していく中で、家庭裁判所を支えていくことが大切である。
弁護士会は司法の一翼を担うだけでなく、家庭裁判所調停委員などを多く派遣し活動しており、家庭裁判所の目的実現のための活動に協力し、改革の理念実現のため,その責任を果たしていくものである。 - 被害者等にも配慮した付添人活動の実施
- (1)子どもの権利条約第40条は、弁護人の選任等適切な援助を受ける権利を規定している。弁護士による少年付添いは、条約の趣旨に沿うものであり、その任務遂行にあたっては、①少年司法手続が適正におこなわれること、②無実の少年が不当な処分を受けないこと、③少年の健全育成を目的として行われることについての配慮が求められる。付添人弁護士としては、このような基本的な任務を遂行するだけでなく、被害者等にも配慮した付添人活動を実施する必要はないかという問題意識のもとに、本項では、被害者等に対する配慮の問題と付添人の活動等について検討する。
- (2)少年法は、保護主義の理念の下、少年の健全育成を目的とするものである。これに対し、近年、犯罪等で被害を受けた被害者等に対する配慮を求める声が高まっているが、少年保護事件においても、被害者等の権利や心情が尊重されなければならないことは当然である。また、付添人の援助の下で行われる被害者等の権利や心情にも配慮した被害回復活動が、少年の内省を深めたり、少年と周囲の者の関係修復を促進したりすることによって、少年の更生にも大きく寄与することがあることも、看過してはならない。
従って、弁護士は、付添人活動にあたり上記のような基本的な任務を遂行するだけでなく、被害弁償や少年からの真摯な謝罪が実現されるよう努めるなど、被害者等の権利や心情にも配慮をした付添人活動を実践すべきである。
また、現行少年法では被害者等への配慮の施策が不十分であるとして、これを充実させるための法改正の議論もあるが、現行少年法の運用状況を見ると、そもそも現行少年法に定められた制度の周知が不十分であるという実情や、家庭裁判所調査官・書記官の被害者等への対応にさらなる改善の余地があるという実情が明らかになっている。
このような現行少年法の運用状況からすれば、法改正により新たな制度を制定する前に、現行少年法の制度が適正に運用されるよう、市民への制度周知を図るとともに、閲覧謄写のための設備の整備や、被害者等に対応する家庭裁判所調査官・書記官の増員などの施策を講じる必要がある。
よって、弁護士及び弁護士会は、少年法の持つ保護主義の基本理念を尊重しつつ、被害者等の権利や心情にも配慮した付添人活動を実践し、かつ、家庭裁判所に対しては、市民への制度周知を促すとともに、閲覧謄写のための設備の整備や被害者等に対応する家庭裁判所調査官・書記官の増員などの施策を講じるよう働きかける必要がある。
- (1)子どもの権利条約第40条は、弁護人の選任等適切な援助を受ける権利を規定している。弁護士による少年付添いは、条約の趣旨に沿うものであり、その任務遂行にあたっては、①少年司法手続が適正におこなわれること、②無実の少年が不当な処分を受けないこと、③少年の健全育成を目的として行われることについての配慮が求められる。付添人弁護士としては、このような基本的な任務を遂行するだけでなく、被害者等にも配慮した付添人活動を実施する必要はないかという問題意識のもとに、本項では、被害者等に対する配慮の問題と付添人の活動等について検討する。
- 関係機関と協力連携し保護主義・福祉主義に立脚した付添人活動の実施
非行を犯した少年が立ち直り、健全に成長発達していくためには、少年の保護者、教師、雇い主など少年を取り巻く人的環境を調整し、社会資源を開拓することが必要である。
そのために、付添人は、保護者等に接触して十分に協議し、働きかけ、少年と保護者等との関係調整的活動を行っていかなければならない。
また、ケースワーク的機能を持つ少年審判において、少年の要保護性を的確に把握し、かつ、その解消を図るためには、心理学、教育学、社会学などの専門的な知識に基づく調査が必要であるし、立場の異なった者の多角的な視点も必要である。さらに、例えば、近時取り上げられている発達障害を少年が抱えている場合などでは、発達障害と非行が直接結びつくものではないものの、付添人活動の上では、弁護士だけでは不十分で、児童精神科医などの専門家の協力が不可欠なケースもあると思われる。
このような少年の要保護性解消のための関係調整的活動の必要性は、原則逆送対象事件といった重大事件でも異なるところはない。2000年改正少年法施行後の原則逆送対象事件の逆送率は、施行前に比べ大幅に増加しているが、付添人としては、逆送決定後の地裁における刑事裁判で少年法第55条による家裁への移送が認められた事案等も踏まえつつ、家裁に対し少年の資質や環境に関する十分な調査を求めるとともに、自らも少年の更生の可能性を信じ、関係者と協力連携した付添人活動により、安易な逆送決定がなされないよう努めるべきである。
また、2007年少年法等改正により、少年院送致可能年齢の下限が従前の14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。しかし、例えば小学生を閉鎖的施設である少年院に収容する必要性を裏付ける立法事実は乏しいというべきであり、付添人としては、14歳未満の触法少年について、今後とも開放的施設である児童自立支援施設における「疑似家族」モデルによる福祉的処遇が有効であることを家裁に訴えていく必要がある。 - 当番付添人制度の全国的実施と国選付添人制度の拡充
少年に対して適正手続を保障するためには、弁護士付添人の選任が不可欠である。しかしながら、長年にわたり、弁護士付添人の選任率は低調を極め、1992年までは1%にも満たないという状況であった。
このような状況下、日弁連は、1998年全国会員による特別会費を財源とした付添人扶助制度を発足させた。福岡県弁護士会は、2001年に、それまでの扶助的付添いを一歩進め、少年身柄事件全件付添活動を開始した。現在では、全件付添いに踏み切った東京三弁護士会を含め、ほとんどの弁護士会が何らかの形で当番付添人制度を導入している。関弁連管内では、近く実施予定の静岡、茨城を含めると全弁護士会が当番付添人制度を実施することとなる。
弁護士会の粘り強い取り組みによって弁護士付添人は急速に増加しており、2006年には観護措置決定を受けた少年事件(14124件)のうち弁護士付添人が選任されたのは3744件(選任率は26.5%)となっている。それでも、成人の刑事事件における弁護人選任率が90%を優に超えるものであることからすれば、まだまだ不十分な状態と言わざるを得ない。また少年の権利である付添人活動が全国の弁護士の拠出金と採算さえ度外視した弁護士の尽力によって支えられていること自体は、弁護士の職責に関連する貴重な活動といえるが、少年付添いはあくまで国によって保障されるべき権利であり、速やかな改善が求められる。また、2007年の少年法改正により、国選付添人制度が拡充されたが、その範囲は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪又は死刑、無期若しくは短期2年以上の懲役・禁固にあたる罪の事件において、鑑別所送致の観護措置決定がされた場合で、かつ、裁判官が必要と認めたときと、極めて限定されたものにすぎない。2005年において、短期2年以上の懲役・禁固にあたる罪の少年保護事件は、1113人であり、観護措置決定を受けた少年1万5476人のわずか7.1%にすぎない。
さらに、2009年には、被疑者国選弁護制度の対象事件が、いわゆる必要的弁護事件にまで拡大されるが、そうなると、被疑者段階では国選弁護人が選任されていた少年の大半が、家庭裁判所送致後は弁護士の援助を受けられないという事態に陥ることになる。少年事件における適正手続を保障する意味でも、このような事態は何としても避けなければならない。
このような状況を打破し、少年の付添人選任権を実質的に保障するために、弁護士及び弁護士会は、今後、当番付添人制度の全国的実施の実現に努めるとともに、国選付添人制度の対象範囲を拡充する法改正が早急にされるよう粘り強く働きかけていく必要がある。
以上