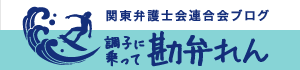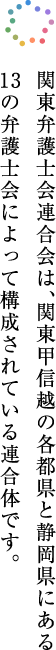
「関弁連がゆく」(「わたしと司法」改め)
従前「わたしと司法」と題しインタビュー記事を掲載しておりましたが,このたび司法の枠にとらわれず,様々な分野で活躍される方の人となり,お考え等を伺うために,会報広報委員会が色々な場所へ出向くという新企画「関弁連がゆく」を始めることとなりました。

漫画家
浦沢 直樹さん
- とき
- 2025年8月8日
- ところ
- 浦沢さんのアトリエ
- インタビュアー
- 会報広報委員会委員 西岡毅
同 委員長 山浦能央
常に新しいジャンルを開拓しながら、独特な世界観と緻密なストーリーで読者を惹きつけてやまない、漫画家の浦沢直樹さん。これまでの数々の名作の制作秘話から、今後の漫画界への想い等を伺いました。
― 幼い頃は、どういうお子さんでしたか。
浦沢さん 僕が生まれてすぐ両親が別居したので、4歳ぐらいまで母子家庭でした。その後、母は、僕を義父母に預けたんですが、不憫に思ったのか、手塚治虫さんの漫画を2冊与えてくれました。近所に友達はいないし、外にも出させてもらえない感じでしたので、その2冊を何度も読みました。それから2年間、絵を描き写したり、著者のサインを真似て書いたりもしていました。
― 2冊の漫画は何でしたか。
浦沢さん 「鉄腕アトム」と「ジャングル大帝」ですね。「鉄腕アトム」がきっかけで、後に「PLUTO」という作品(※「鉄腕アトム」の中の1エピソード「地上最大のロボットの巻」をリメイクした作品)を描きました。「ジャングル大帝」は、主役のレオがすでに大人になっている巻だったんですが、レオがどういう経緯でジャングルを治めるようなライオンになったのか、勝手にそれまでのストーリーを想像したりして、それが今に生きているかもしれません。でも、僕は、その頃ちょっと危なかったんです。友達がいないから、おばあちゃんの三面鏡に自分を写して、それをスミス君と名付けて、ずっとスミス君と会話していました。1人で2人分、別の視点から話してました。
― 今でも、漫画を描くときに、客観的に自分以外の視点で見たりしますか。
浦沢さん ほぼそうですよ。自分の視点ってなんかよく分かんないですよ。だから僕の漫画って、群像劇的な作品が多いのは、その頃培われたんじゃないですか。
― 子どもの頃からオリジナルの漫画も描かれていましたか。
浦沢さん はい、8歳の時に初めて完成させた長編漫画「太古の山脈」のストーリーは、ある大富豪の息子が家出して、山を登って行ったら、大きな穴に落ちる。でも、下が湖で助かった。そしたら、その地下に恐竜がいるような太古の山脈があって、そこに貴重な鉱脈があって、悪い軍団が地上の世界で拉致してきた人たちを奴隷のように働かせていたんですよ。最後は、その若者が悪い軍団の親玉と戦って、相打ちで死ぬというお話でした。
― そのお話が次回作の構想ではなくて、8歳の頃の作品とは驚きです。当時から今のような絵柄でしたか。
浦沢さん タッチは全然変わってます。手塚治虫さんとか、石ノ森章太郎さんとか、さいとうたかをさんのような劇画タッチまでいろんな人に影響を受けてるから。
― 映画等の影響も受けましたか。
浦沢さん 8歳の頃、テレビの洋画劇場でフランス映画を立て続けに観て、ジャックベッケル監督の「穴」、アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督の「恐怖の報酬」の2本がすごく心に残っていて、1回しか観てなかったのに、大人になってDVDで観たら、頭の中にあった映像のまんまでした。僕の頭の中には、見たものがファイリングされて収納されていて、それを引き出してきて漫画に描いている感じです。漫画家になってから、アシスタントに資料室から写真を持ってきてもらうときに、道路、建物、車の様子を絵に描いて指示したら、その絵と写真が写したようにぴったりだった事が何度かありました。
― 作品を描かれるとき、頭の中で音楽は流れますか。
浦沢さん 鳴ってるでしょうね。漫画って音楽を鳴らせないから、作品からBGMが聞こえるようにと描くわけです。でも、映画やドラマでは音楽が流れていて、あんな曲を流したら感動するに決まっているよー、と羨ましく思いますね(笑)。
― 中高生の頃も漫画を描かれていたんですか。
浦沢さん その頃から、音楽と陸上を始めてるんですけど、いつ描いたか分かんないぐらいどんどん漫画が増えてるんですね。漫研の人より描いてたんじゃないかな。
― 学生の頃、ご自身のオリジナル漫画の評判はいかがでしたか。
浦沢さん 例えば、親戚のおじさんが僕の漫画を見て、「プロの漫画家になれる」って言うんですけど、自分で、これではプロになれないって分かってたんです。だから素人の中途半端な褒め方には、すっごいイライラしてました(笑)。
― 当時、将来は漫画家志望だったんですよね。
浦沢さん ずっとなりたくなかったんですよ。漫画家というのは、眠れない、忙しいとか大変な話ばっかりなので。あと、あまりにプロの水準が高くて、僕なんかがやれるようなもんじゃないと思っていて、中学、高校、大学と、次第に確固たるやりたくない感が高まってきた(笑)。なぜなら、どうやらプロになると、「売れるものを作れ」っていうのを出版社、編集部から言われると。売れる漫画を描くなんて、もう冗談じゃない。僕は子どもの頃から売れ線の漫画にあまり興味がなくて、それは今もずっとそうですね(笑)。
― 例えば、「☓☓☓」(※ 掲載自粛)のような最近のヒット作は読まれますか。
浦沢さん 一応研究のために読んだりしますが、1巻読み切れなかった(笑)。
― 就活が近づく大学3〜4年の頃にはさすがに漫画家志望でしたか。
浦沢さん 就活前の大学3年の時点で、ちゃんと原稿の形になってた漫画が2〜3作品あったんだけど、秋の学園祭のライブが終わって、機材を片付けながら、「そろそろ1本これだっていう漫画を描きたい」ってふと思ったんです。どうせ就職して社会人になったら、漫画は描けないだろうからと。ただ、出版に関する仕事には就きたかったので、講談社と小学館は受けようと思ってたんですね。それで、当時のバイトの合間に、置いてあった漫画本をぱっと見たら、小学館の新人持ち込み歓迎みたいな頁があったので、それを破って持ち帰りました。そこに編集部の電話番号が書いてあったので、編集部に電話して、就職活動用の履歴書の提出のついでに、漫画の持ち込みのアポイントメントも取っておいたんですよ。
― 同じ日に就職活動と漫画の持ち込みをなさったんですね。
浦沢さん ネクタイ締めて髪の毛きちんとしたそんな格好で漫画の原稿を持って来たのは初めてだよ、と言われました(笑)。小学館の受付に就職活動用の書類を提出して、そのまま、漫画の編集部に行ったら、2年目ぐらいの若手の編集者が、「なんでこんな奇を衒った作品ばかり描くんだろうねー。」とか言うんですよ。漫画なんて奇を衒わななきゃダメだろとか思いながら聞いてました。なにしろこっちは漫画キャリア長いですからね。編集2年目のあちらより(笑)。それで、やっぱりメジャーの小学館なんてこんなもんだと思って立ち上がろうとした瞬間に、後ろからベテランの方が、「ちょっと見せてごらん」と、パラパラやって、「あ、これはサンデーじゃないよ、ビッグ行こう」って言って、その時創刊だったスピリッツの編集部に連れて行かれて、そこで小一時間褒められました。ちなみに、そのベテランの方というのは、後にビッグコミックオリジナルの編集長になる人で、「パイナップルARMY」とか「MASTERキートン」をやろうと言ってくれた方です。
― その後の経緯はいかがですか。
浦沢さん 1週間ぐらいして電話がかかってきて、「新人賞締め切ったんだけど、この間の原稿を今日持ってきてくれたらねじ込むので。」と言われたので、小学館に原稿を持っていきました。そこから1ヶ月くらいかな、また電話がかかってきてなんと「新人賞入選です!」と。編集者の採用試験は落ちたんですけどね。その時、おもちゃのデザイン会社の内定は出てたんで悩みましたけど、父親に、「新人賞取ったから1年間だけ漫画やってみようかな」と相談したら、「やってみりゃいいじゃん」って。1年経って芽が出なかったらやめようと思って、一応プロの漫画家として描き始めたら40年以上経ってしまった、という感じですね。
― 先程の「パイナップルARMY」と「MASTERキートン」ですが、ああいった作品は、専門知識が大変そうですね(※前者は、市民を軍事訓練する元傭兵の話。後者は、特殊部隊を除隊後、考古学者を目指している保険調査員の話)。
浦沢さん いや、知識というのは調べたら分かるんですよ。それよりもドラマなんですよ。知識は、漫画を装飾するために、いわば調味料のように入れてるだけだから。軍事系でも、考古学でも、その筋の方に聞けば教えてくれるじゃないですか。それよりも重要なのは、ストーリーやキャラクターの設定とか、この世にない創作の部分なんですよ。
― その2作品と同時期の作品の「YAWARA!」(※天才柔道少女の話)は、設定が全然違いますよね。
浦沢さん 「YAWARA!」の連載前、いわゆる売れる漫画ではなく、漫画の新しい地平を作ろうと思っていたので、ミステリー作品を頭に描いてたんです。それで、担当編集者と打ち合わせするとね、今日のスポーツ新聞の話はすごく楽しそうなんだけど、本題の僕のミステリーの話では、急につまらなそうなんです。だから、ちょっと楽しそうな顔をさせたいと思って、当時の女子柔道があまりに人気がないスポーツだったんで、本当に冗談で、「女子柔道漫画でも描きましょうか」って言ったんですよ。
― 冗談がきっかけだったんですね。「YAWARA!」の主人公の設定はどのように考えられたんですか。
浦沢さん 従来のスポーツ漫画は、努力、努力でしたから、もう努力しない、天才的に最初から強いっていう設定にしました。そういう新しい視点の漫画だったので、あの大ヒットになったと思います。ちなみに、「ローマの休日」(※王女と新聞記者の恋物語の映画)に、オードリーヘップバーンの王女様とそれを追っかける新聞記者が出てきますが、実は、「YAWARA!」はそれが元ネタです。あと、「奥様は魔女」(※魔女の妻の日常を描いたドタバタコメディドラマ)で、鼻をピクってやって魔法を使うじゃないですか。それが、背負い投げをポンって決めるイメージに繋がりました。
― 「YAWARA!」は、田村亮子選手(※現・谷亮子 五輪女子柔道2度の金メダリスト)のニックネームにもなりました。
浦沢さん 単行本が10巻ぐらいのときでしたか、田村亮子選手の試合を見てたら、観客席に横断幕で「福岡のヤワラ」って飾ってあって、テレビでも「ヤワラちゃん」とか言ってるんですよ。おいおいと思いつつ試合見てたら、パーンって背負い投げですっ飛ばしたりするじゃないですか。あんな凄い子いなかったんですよ、それまでは。漫画でしかできない技だと思って僕描いてたから、これから漫画描きづらくなると思いましたね。
― 大ヒット作でしたので、もっと連載を続けようとは思いませんでしたか。
浦沢さん 元々バルセロナ五輪まで描いたら終わりって言ってたんですよ。他に描きたい作品があるので早くそっちを描きたい、と。そうしたら小学館の偉い人たちがゾロゾロ来て、やめないでくれ、続けてくれと言うんですよ。出せば100万部超えっていう本を終わらせるのは、業界的に考えられない。「ミステリーやりたい」と言ったら、「絶対に売れない、今まで売れた試しがない」って言うんですよ。編集部って過去の判例に従おうとするんです(笑)。もう一本、女の子が主人公のスポーツ漫画を描いてほしいって。
― それが「Happy!」(※テニス少女の物語)ですね。
浦沢さん 1つ売れると、その大量生産が始まるんです。僕はそれを壊したい。ちなみに「Happy!」は「YAWARA!」ほど売れなかったので失敗作のように言われる向きもありますが、「そんなに女の子のスポーツものを描いて欲しいなら描きますが、そのかわり売れませんよ。2割7分ぐらいのバッターまではいくかもしれないけど」って宣言して始めたから、自分の好きなやり方ができたんで、僕、実は一番好きなんですよ。「YAWARA!」と同じように女の子が主人公で、わざと二匹目のドジョウに見えるようにして、売りにきたって思わせておいて、実は、真逆のことを実験的にやってるわけですよ。
― 次作の「MONSTER」(※天才医師が連続殺人事件の犯人を追うというストーリー)はいかがでしたか。
浦沢さん 「Happy!」の連載は続いていましたが、「MASTERキートン」が終わったタイミングで、いよいよ僕のやりたいことを始めたいと。これはもう、第二のデビューという気持ちです。ずっと子どもの時から漫画の革命を起こすんだと思ってたから。それで、いよいよ「MONSTER」のストーリーが出来上がってくるんですけど、また、編集部から、「絶対に売れないんで、4巻で終わらせる心づもりで始めてくれ」と言われたんですが、いや、とにかく頭の中に面白い漫画があるんだから見てなさい、って気持ちで始めたんです。ちなみに、「MONSTER」って名付けたのは、あの作品自体がモンスター級だって言われるようになるための自分に対する負荷でもあったんですよ。
― タイトルを見たとき、怪物の話かと思っていました。
浦沢さん 僕は、我々地球人の話を描きたいんです。素晴らしい進化は遂げたかもしれないけど、ローマ帝国に始まり、戦国時代やら、宗教間でずーっと続く争い事、しまいには原爆投下、そんな愚かしい歴史を背負いこんだこの地球を舞台に、ドラマという大嘘のエンターテイメントを描きたいんです。この重力のある我らの地球上のドラマをね。
― 創作というのは、いわば嘘ですよね。
浦沢さん ただ、リアルの部分はね、徹底的にリアルに描くんです。なぜかというと、大嘘が嘘っぽく見えないようにするためなんです。今は、「あさドラ!」っていう漫画(※少女の成長と怪獣騒動を描いた作品)を描いてますけど、怪獣が出てきますので、生物学者の方にちゃんと取材したりしてるんです。こんな怪獣は存在しえますかって。最初にワクワクするような大嘘あり、次にその大嘘をリアルにするための取材が始まるんです。例えば、「MONSTER」のドクター天馬が、外でメスで手術するシーンなんて絶対にありえない。いろんなお医者さんに取材して回りましたが、外で手術したら、100%感染症になるんですよ。
― 次の作品は「20世紀少年」(※子ども時代の空想が現実に起きるという話)ですが、これは単行本のネタバレですけど、招待状のアイディアは誰が考えたんですか。
浦沢さん あれは、担当編集者ですね。あの頃になってくると、僕の悪ふざけに、若い編集者たちも乗っかって楽しんでくれるっていう雰囲気がありました。ちなみに、招待状の位置は指定できないので、本ごとに挟まっているページは違ったんですが、それぞれ別の衝撃があったようです。面白かったですね。
― 一般的なこともお聞きしたいんですが、最近隆盛の電子書籍はどう思われますか。
浦沢さん 僕の漫画の電子配信が結構遅くなったのは、やはりスマホは漫画を読む道具ではない、という思いからですね。縦スクロール漫画などというものもありますが、あれは明らかに漫画の退化ですしね。手塚先生を始め、その先達の方々が悪戦苦闘して、見開きの紙の上でどう表現するかと試行錯誤してきたことを、全部台無しにしてしまった感じがしますね。文明の利器が文化を壊すってことがあるんだなっていう風に非常に思います。
― 無料の電子漫画の台頭は、漫画の売上への影響もありますよね。
浦沢さん 今は、単行本が1万部売れると万々歳と言われているんですよ。漫画家は、材料費払って、アシスタント雇って、ご飯食べさせて、仕事場借りて、というように、製作費は全部自分持ちなんですよ。もちろん出版社から原稿料が出ますが、制作費を埋めるほどの金額じゃない。あとは単行本の印税ですが、単行本1冊600円くらいとすると、印税は10パーセント、1冊売れて60円、1万部売れても60万円しか入らないんですよ。本1冊出すには1年、2年かかりますから。ある一部の大ヒットした漫画を指して、漫画家儲かるって言ってますけど、まあ商売になってない人だらけですよ。だけど、その中でも大事なのは、漫画家は出版社から自主独立して作品を作ってるんだということをもっと意識すべきです。
― 出版社と対等に張り合うのは大変ですよね。出版契約書ってあるんですか。
浦沢さん ちゃんと出版契約書が交わされるようになったのは90年代に入ってからじゃないかな?それまでは本当に口約束みたいなもので。ちなみに、当初の出版契約書は出版社に有利な内容でしたので、顧問弁護士の方とも協力して、全部を作り直しました。その契約書がひな形になればいいなって思ったんですが、何も言わない他の漫画家や、まだ強く主張ができない若手の漫画家に関してはずっとそのままなんですよね。僕は、若いとき、いつか意見できるようになろうって、月6回の締め切りとか頑張って守ってきましたねぇ。
― 最後に、今後の日本の漫画界に期待することはありますか。
浦沢さん 漫画家は自分が独立の存在であると自覚して、編集部に誘導されて描くんじゃなく、自分から新しいものを作るんだっていう気概を持つべきですね。それで読者の方は、いわゆるメディアミックス的に宣伝されるものではなく、埋もれてしまっている素晴らしい作品を探しに行ってほしいです。漫画家と読者で、ぐっと文化をあげようっていうのを自覚的にやらないと。産業に押しつぶされるっていう感じはもったいないです。
― 今日は、長い間、楽しいお話をありがとうございました。