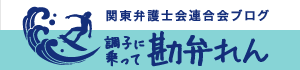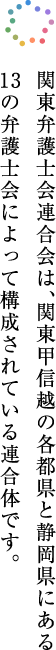
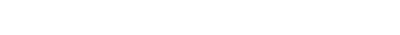 宣言・決議・意見書・声明等
宣言・決議・意見書・声明等
2025年度(令和7年度) 大会宣言
大会宣言
宗教団体をめぐる法的課題に関する宣言
2022年7月に発生した安倍晋三元首相の銃撃事件と同事件を契機として世に広く知られるようになった宗教等二世問題、今年3月で地下鉄サリン事件から30年目を迎えたが未だ収束しないオウム真理教をめぐる一連の問題、今年3月に東京地方裁判所で解散命令が出された世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐる問題など、昨今、宗教をめぐる重大な問題が数多く散見されるようになった。このような宗教団体の一連の問題の背後には、宗教団体における組織運営、ガバナンスの問題など、宗教団体をめぐる法的課題が多数存在している。また、地方の宗教団体の中には、人口減少、過疎化などにより、その存続それ自体が危ぶまれている団体もある。このような情勢の下に、当連合会は、次のとおり宣言する。
- 1 当連合会は、宗教団体に対し、宗教団体が人の死生観に深く関わる宗教活動を行っていることを踏まえ、法令遵守・ガバナンスの更なる向上に取り組むことを求める。
- 2 当連合会は、管内各弁護士会と共に、宗教団体の健全な維持・活動のため、法令遵守・ガバナンスの向上のみならず、創設、承継、清算等の法的な課題の検討及び助言に関与し、積極的な支援に取り組むことができる体制の整備を進めることに努める。
- 3 当連合会は、管内各弁護士会及び管内各弁護士と共に、オウム真理教事件を過去のこととして風化させず、現在も継続している法的な問題として対応することに努める。
- 4 当連合会は、管内各弁護士会と共に、「宗教等二世」に対する法的な支援が必要な場面において、その支援が提供できるような体制の整備を進めることに努める。
- 5 当連合会は、国に対し、宗教団体に関する現行法での被害者救済が不十分な部分に対して、立法的な解決を実現するための取り組みを進めるよう求める。
2025年(令和7年)10月3日
関東弁護士会連合会
提案理由
-
1 宗教団体の健全な維持・活動のため、その法令遵守・ガバナンスの向上を支援すること
-
(1)宗教・宗教団体の存在意義
現在、日本には約17万9000の宗教法人が存在し、その他にも多数の宗教団体が存在している。また、各宗教団体からの申告による信者数の合計は、約1億7220万人となる(宗教年鑑令和6年版)。
宗教や宗教団体は、人の精神的な支えや心の拠り所を提供するだけでなく、儀礼・年中行事を通じた地域の結びつきや地域の人々の交流、文化や伝統の継承、貧困者・困窮者への支援や災害時の被災者支援等の社会貢献活動などの役割を担ってきた。現代においては、宗教が提示する道徳や倫理観が、科学技術の急速な進歩に対しての歯止めとなるという新たな側面も指摘されている。
また、特に重要な点として、宗教と死生観は密接に結びついており、多くの宗教で、死や死後の世界、魂の存在などを教義に含んだり、死に関する儀式を備えていたりする。それによって、宗教は、死の問題について一定の答えの提供、死を前提とした人生の指針の提示、喪失への癒やし(グリーフケア)などの一端を担っている。墓地の運営は、行政と公益法人を除けば宗教法人のみが行うことができる。
このように、宗教や宗教団体は、現代においても人や社会にとって大きな存在意義を有していると言える。宗教団体に宗教法人として法人格が与えられているのも、その公益性ゆえである。 -
(2)宗教団体が直面している法的課題
現在、宗教団体は、多くの法的課題に直面している。
宗教団体の規律は多くが教義等に基づいており、宗教法人においても宗教法人法だけでなく各法人が定める規則に重きが置かれている。また、行政には管理運営に関する一般的な監督権が与えられていないため、健全な運営や活動を行うための体制が不十分な場合や必ずしも民主的な運営がなされていない場合があり、団体内部での不正や不祥事が生じやすいと言える。特に、無住寺院などでは、当該法人の運営・管理を行う代表役員等が不在となっている場合もあり、実質的に団体の管理運営が十分に行われていない団体も存在している。
また、宗教の伝統的な価値観と現在の価値観との相違により、労務関係、消費者契約、賃貸借契約等でトラブルとなる場合や、反社会的勢力が宗教法人を隠れ蓑に脱税やマネー・ローンダリング、墓地経営等の営利事業によって不正な利益を上げているケースもある。
さらに、少子高齢化や地域の過疎化、核家族化などにより宗教離れが進行し、不活動宗教法人の増加が指摘されている。不活動宗教法人の放置は、第三者により宗教法人が不正取得され、宗教法人格が悪用されるおそれがある。宗教離れの問題は、信者数の減少とそれに伴う収入の減少にもつながっており、単独での宗教団体の維持が困難となり、宗教法人同士の合併や宗教活動以外の営利活動を行う団体も増加している。
墓地をめぐっては、墓じまいや改葬、都市部における墓地の不足、名義貸しと思われるような墓地経営、墓地や納骨堂の経営破綻などの問題が生じている。
そして、一部の宗教団体においては、霊感商法などの反社会的行為、不当な手段による勧誘や脱会に際してのトラブルなどが生じ、大きな社会問題となっていることは改めて指摘するまでもない。 -
(3)宗教団体に期待されること
前述のとおり、宗教及び宗教団体には大きな存在意義があり、信者にとっては安心して信仰できる環境が整備されていること、社会にとっては宗教団体が信頼できる公共的存在であることが重要であり、そのためには宗教団体が社会的な正当性を確保しながら長期的に安定した運営がなされていることが不可欠である。
宗教団体は、その教義や儀礼等によって、人や社会に大きな影響力を有しており、特に人の死生観という非常に根源的かつ繊細な問題に深く関わる活動を行っているという自覚を持った上で、それに見合った責任ある行動をとる必要がある。そのためには、宗教団体には、適切な運営がなされるよう団体内部でのガバナンスが十分に図られ、団体存続のための適切かつ継続的な取組がなされ、信者等に対する人権尊重や、違法または反社会的な行為を排除することが期待される。 -
(4)支援体制の整備
このように、現代において宗教団体が直面している課題は様々であり、目の前の課題を解決するのみならず、「そもそも何が課題であるのか」という課題の設定が適切に行われていくことも必要である。しかし、多岐にわたる課題を宗教団体のみで適切に設定することは容易ではなく、支援の専門家が課題の設定、解決策の立案及び実行を支援することが重要である。
弁護士は、日頃から信教の自由を含む人権擁護活動に取り組んでおり、また法的課題を見出すために必要となる事実認定力及び多角的分析力を日々の業務を通じて磨いている。そして、宗教団体の創設、活動継続・発展、事業承継、廃業・清算の各場面において、信教の自由に配慮しながら、的確な課題の設定及び解決の支援を行うことが可能である。
宗教及び宗教団体の存在意義は大きく、実務法曹としての弁護士がこのような支援を行うことは、宗教団体の健全な運営にとって非常に重要であり、弁護士が積極的に取り組むことが必要であり、当連合会としても、管内各弁護士会と共に、これを支援できる体制の整備を進めることが重要である。
-
(1)宗教・宗教団体の存在意義
-
2 オウム真理教事件を風化させないこと
- (1)オウム真理教による地下鉄サリン事件から30年の節目の年を迎えた。
時間の経過と共に弁護士を含む多くの国民がオウム真理教事件を「過去」のことと位置付け、すべてが解決されたものと捉えがちである。しかし、現在もオウム真理教の問題は続いていることを忘れてはならない。 - (2)特に、地下鉄サリン事件を始めとした凶悪な刑事事件に巻き込まれた被害者の賠償は未だ果たされていない点が挙げられる。
オウム真理教事件の被害者やその遺族に対しては、1996年3月のオウム真理教の破産宣告以降、破産管財人による配当やサリン事件等共助基金による配当、また、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律による給付などにより金銭的な賠償がなされてきた。
だが、30年が経過した現在も未だ100%の賠償は果たされていない。
すなわち、2000年に破産管財人がオウム真理教の後継団体である現Aleph(アレフ)との間で、アレフが被害者の破産債権の残額を引き受ける旨を合意し、これをオウム真理教犯罪被害者支援機構が破産管財人から債権譲渡を受けてアレフからの回収金を被害者への配当に充てるべく活動をしている。
しかし、東京地方裁判所にて2019年4月にオウム真理教犯罪被害者支援機構のアレフに対する約10億2500万円の損害賠償請求が認められ、2020年1月には最高裁判所で当該判決が確定したにもかかわらず、アレフから任意の支払はなく、差押えによっても遅延損害金の一部が回収されたのみで満額の回収にはおよそ至っていない。
オウム真理教事件の被害者の中には30年経った現在も後遺症で苦しむ人がおり、また、大切な人を亡くした遺族の悲しみは癒えていない。 - (3)また、アレフを含むオウム真理教の後継団体は、現在も依然として元教祖等の影響下にあると言われ、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づいて公安審査委員会による観察処分及び再発防止処分が継続している。
だが、各団体ではオウム真理教事件に関する知識の少ない30歳以下の若い世代を主な対象とする勧誘活動が行われ、新規構成員の割合が増加している。
このような中で各団体の施設が存在する地方自治体や地元住民は、現在も条例の制定や抗議集会を開催するなどして後継団体への対応を迫られている。 - (4)以上のとおり、被害者や遺族に対して30年が経過した現在も未だ賠償が果たされずにいること、また、後継団体に対する観察処分又は再発防止処分の継続など後継団体をめぐる問題が発生していることを改めて認識し、当連合会は、管内各弁護士会及び各弁護士と共に、オウム真理教事件を「過去」のこととして風化させず、「現在」も続く問題としてとらえ直さなければならない。
- (1)オウム真理教による地下鉄サリン事件から30年の節目の年を迎えた。
-
3 「宗教等二世」に必要な場面で法的支援ができるよう体制の整備を 進めること
一般的に、特定の宗教を信仰する保護者の下で、その信仰を強いられ又は宗教上の教義の影響を受けて育つ立場の者は宗教二世と呼ばれているが、ここでは、保護者が属する宗教以外の団体等の教義ないし思想による影響を受ける子どもを含め、「宗教等二世」と呼ぶ。
1995年3月にオウム真理教の教団施設に強制捜査が行われ、同施設内で劣悪な環境に置かれていた多くの子どもたちの存在が明らかとなった。彼らがオウム真理教により与えられた影響は計り知れないにもかかわらず、彼らに十分な手当てがなされた経過はなく、彼らを含む「宗教等二世」問題は、長い間社会的に見過ごされてきたといえる。
昨今、旧統一教会の問題が浮き彫りになる中で「宗教等二世」の存在が広く認識され、ようやく支援の必要性などが説かれるようになってきた。また、地下鉄サリン事件から30年が経過し、改めてオウム真理教の問題が取り上げられる中で、彼らの多くが今も心の傷を抱えながら生活していることが明らかとなった。
当連合会は、管内各弁護士会と共に、宗教等二世問題が重大な人権侵害であり社会問題であるにも関わらず、長く彼らの苦悩に向き合うことを怠ってきた社会の責任を重く受け止め、法的支援が必要な場面において、それを提供できるよう体制の整備を進めるよう努める所存である。 -
4 現行法での救済が不十分な部分に対して立法的な解決を図るべきであること
同じく旧統一教会の問題をめぐっては、宗教法人の解散命令確定後における清算人の権限が十分でないため清算業務が円滑かつ実効的に進まない可能性があること残余財産が旧統一教会が指定する他の宗教法人に帰属する結果、現在は被害の主張はしていないが、将来、被害があったと声を上げてくる被害者に対し救済が不十分になるおそれなどが指摘されている。
オウム真理教の破産手続の中では被害者救済に向けて様々な立法的解決が試みられ、一定の被害者救済に繋がったという前例がある。
例を挙げれば、破産法上、国の債権は財団債権として被害者の損害賠償請求権(破産債権)よりも優先されるところ、それでは被害者の救済に繋がらないとして「オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律」が制定され、被害者の債権を国の債権よりも優先させることとし、被害者への配当率が上昇した。さらに、オウム真理教による財産隠しに対しては「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」が制定され、特別関係者が有する財産に対して否認権の行使が容易にできることとなった。そして、「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」では、被害者救済を図るために国が最大3000万円の給付金を支給する手当がなされた。
これらは現行法では十分な被害者救済に繋がらないことが問題視され、破産管財人や被害対策弁護団らの国会への働きかけによって実現された施策である。
旧統一教会をめぐる宗教法人の解散命令確定後の清算や残余財産の帰属などの問題に関しても、現行法による解決では不十分である。このようにオウム真理教の破産手続において立法的解決により被害者救済が図られたことも踏まえ、この問題について、国は、特例法を制定するなどの立法的解決を実現するための取り組みを進めるべきである。