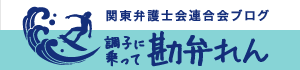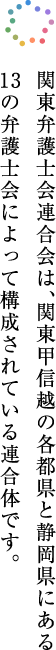
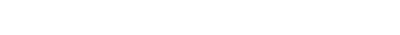 宣言・決議・意見書・声明等
宣言・決議・意見書・声明等
2025年度(令和7年度) 大会決議
日本国憲法の恒久平和主義を改めて堅持することを求める決議
世界情勢が不安定化している中にあって、「再び戦争の惨禍が起ることのないやう」日本国憲法が採用した徹底した恒久平和主義を改めて堅持することを求める。
2025年(令和7年)10月3日
関東弁護士会連合会
提案理由
-
1 安保法制、敵基地攻撃能力が憲法に反すること
-
(1) 日本国憲法が採用する徹底した恒久平和主義
日本国憲法は、「戦争は最大の人権侵害である」という戦争に反対する思想と、アジア・太平洋戦争の惨禍に対する痛切な反省から、憲法前文において「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・日本国民は、恒久の平和を念願し、・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とうたい、武力による威嚇または武力の行使を永久に放棄し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦権を認めない(9条2項)との規定を置き、世界に例を見ない徹底した恒久平和主義を採用している。 -
(2) 強まる戦争当事国化の危険
上記恒久平和主義のもとで、政府は、自衛隊が創設された1954年以降、自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は「戦力」に該当しないとの解釈のもと、個別的自衛権は認められるが、他国防衛を本質とする集団的自衛権の行使は認められないと一貫して説明してきた。
ところが、2015年9月19日に当連合会や各弁護士会が繰り返し違憲性を指摘してきた集団的自衛権を容認する安全保障関連法制(安保法制)が強行採決により成立した。
その後、2022年12月には安保三文書の改定が閣議決定され、敵基地攻撃能力を保有し活用していく方針が明記された。
安保法制のもとで敵基地攻撃能力が発動される場合、それは、日本が武力攻撃を受ける危険が一切生じていない状況であっても、集団的自衛権の行使として、すなわち他国防衛のために敵基地を攻撃するということを意味するのであり、これにより日本が戦争の当事国となるばかりでなく、日本の領土に対して反撃がなされるリスクは、敵基地攻撃に至らない集団的自衛権行使にとどまった場合と比較しても大きくなるものと考えられる。
そして、最近でも、特に南西諸島において駐屯地、ミサイル部隊が新設されるなど「防衛体制」の強化が進んでいる。
2015年9月の安保法制の成立を契機に、日本が戦争の当事国となる危険性は日に日にましているといえる。
当連合会は、安保法制、敵基地攻撃能力ともに、その違憲性を指摘し撤回を求めてきたところであるが、安保法制成立から10年目の本年、上記「防衛体制」の強化が、恒久平和主義を採用する憲法に反し、日本を戦争当事国化する危険を有するものであることを再確認する必要がある。
-
(1) 日本国憲法が採用する徹底した恒久平和主義
-
2 防衛関係予算の増加が国民生活に与える影響
-
(1) 右肩上がりの防衛予算
「防衛体制」の強化は、その組織面、能力面のみが問題となるものではない。これらを支えるだけの予算を必要とする。
政府は防衛費をNATO並みのGDP比2%にすることを目指し、2022年12月16日に閣議決定された「防衛力整備計画」において、2023年度から2027年度まで5年間で総額43兆円もの防衛関係費を計上する方針が示された。実際に「防衛力整備計画」に基づき、2024度の防衛関係予算は7兆7249億円(対前年度比+17.0%)、2025度の防衛関係予算は8兆4748億円(対前年度比+9.7%)と右肩上がりに増加している。 -
(2) 厳しさを増す国民生活と防衛費増加の影響
他方で、国民生活を見れば、厚労省の「毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報」によると、現金給与総額(事業所規模5人以上)での実質賃金指数は、前年から-0.3%である。3年連続での前年比マイナスとなっていて、近年の食料品やガソリンの値上がり、最近の米価格の高騰等、物価上昇に賃金上昇が追い付いておらず、国民の生活を取り巻く環境は厳しさを増している。
このまま防衛関係費が増加すれば、必然、他の予算削減が進み、その結果、国民生活に関連する予算が縮小されることとなる。長期にわたる経済・産業の停滞、今後さらに進行する少子化による人口減少などにより国力の縮小が不可避である日本において、国民・市民生活を犠牲にせずして右肩上がりの防衛関係費を負担し続けることは不可能である。防衛関係費の増加を許せば、一層の増税や社会福祉費の切り下げは避けられず、国民生活に多大な悪影響が出ることとなる。
-
(1) 右肩上がりの防衛予算
-
3 日米一体化と「台湾有事」
イスラエルとパレスチナ間の紛争、ロシア連邦によるウクライナ侵攻、そして本年にはイスラエルがイランを攻撃し、これをアメリカが支援するなど世界情勢が不安定化してきている。しかし、だからといって安易な軍備増強論や核兵器共有論に傾けば、日本は平和主義を捨て去ったというメッセージをこれまでよりもさらに強く世界、特に周辺アジア諸国に発信することとなり、アジアの緊張と世界の不安定化を加速させるだけであることは当連合会が2022年度の決議「改めて日本国憲法の恒久平和主義及び国是である非核三原則を堅持することを求める決議」において指摘したとおりである。
この点、2025年3月には陸海空の自衛隊を一元的に指揮する常設の統合作戦指令部が設置された。同司令部は、昨年7月の日米安全保障協議委員会(2+2)共同発表によれば在日米軍をインド太平洋軍司令官隷下の統合軍司令部として再構成し、そのカウンターパートになることが計画されていて、米軍との一体化が進んでいる。そして、報道によれば、「台湾有事」の際には、米軍のミサイル部隊を南西諸島、フィリピンに展開させる方針とのことであり、現に南西諸島では、駐屯地、ミサイル部隊が新設されている。
このように「台湾有事」への対応の名のもとに日米一体化が進んでいる。しかし、敵基地攻撃能力を保有した上での集団的自衛権の行使が日本を戦争当事国化する危険性は上述のとおりであり、日米一体化の中で、日本が戦争当事国化する危険性が増している。
しかし、戦争は最大の人権侵害であり、絶対に始めてはならないというのが日本国憲法の理念であり、また歴史の教訓である。イスラエルとパレスチナ間の紛争、ロシア連邦によるウクライナ侵攻、アジア・太平洋戦争中の日本を見ても、一度始めた戦争・紛争を終わらせることは極めて困難である。戦争・紛争が続く間犠牲者は増え続け、そしてその犠牲者は当事国の国民である。
だからこそ、日本国憲法は「再び戦争の惨禍が起ることのないやう」徹底した恒久平和主義を採用し、日本が戦争当事国となることのないよう歯止めをかけている。 -
4 結語
以上みてきたとおり、2015年の安保法制の成立後、日本の「防衛体制」は変貌し、日本が戦争当事国となる危険性は現実的なものとなっている。また、「防衛体制」の強化に伴う防衛関係予算の増加が国民生活に与えるであろう影響も看過できない。
世界が不安定化している中で、また世界が不安定化しているからこそ、今、改めて日本国憲法の恒久平和主義の重要性を再認識し、日本が戦争当事国となることがないよう恒久平和主義を堅持する必要がある。